
障害福祉サービス事業所 ぐろーあっぷ 様
障害福祉サービス事業所 ぐろーあっぷ WEBサイト
- ウェブサイト制作


障害福祉サービス事業所 ぐろーあっぷ WEBサイト

隼人環境総合 コーポレートサイトリニューアル
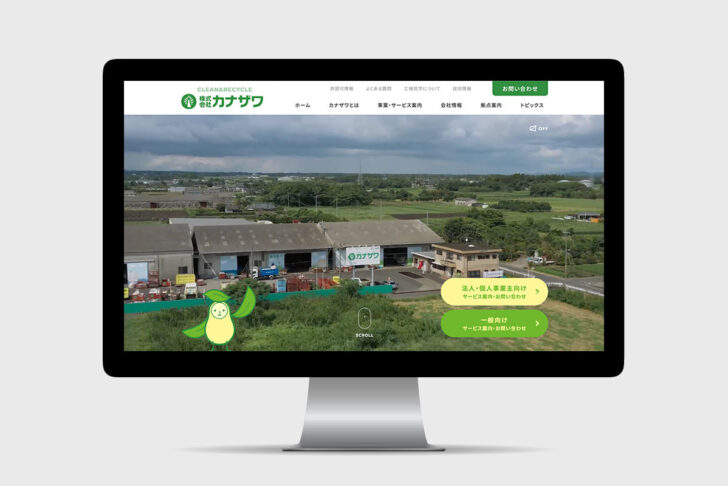
カナザワ コーポレートサイトリニューアル

CLAVIS ウェブサイトリニューアル

プランテムタナカ コーポレートサイトリニューアル

上原機器 ウェブサイト
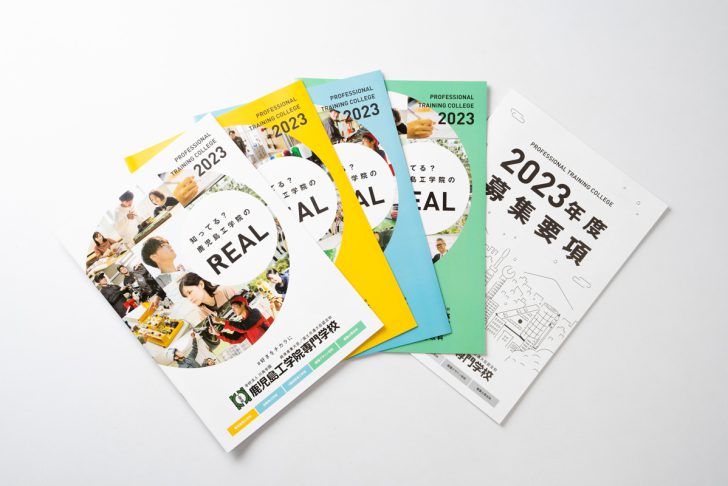
鹿児島工学院専門学校 学校案内&募集要項パンフレット
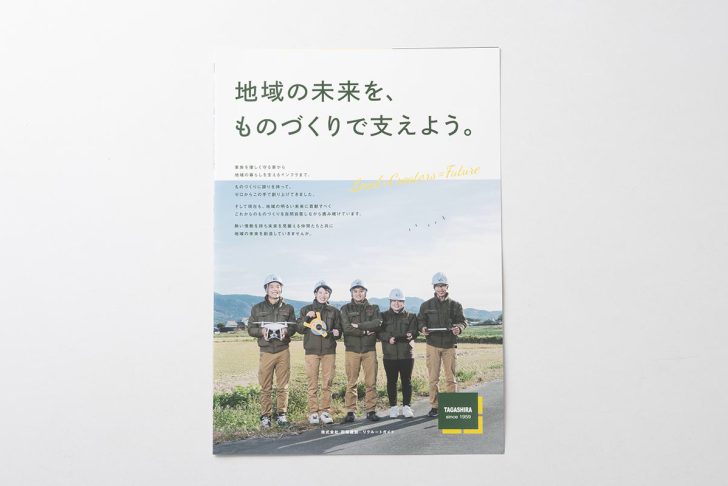
田頭建設 リクルートガイド
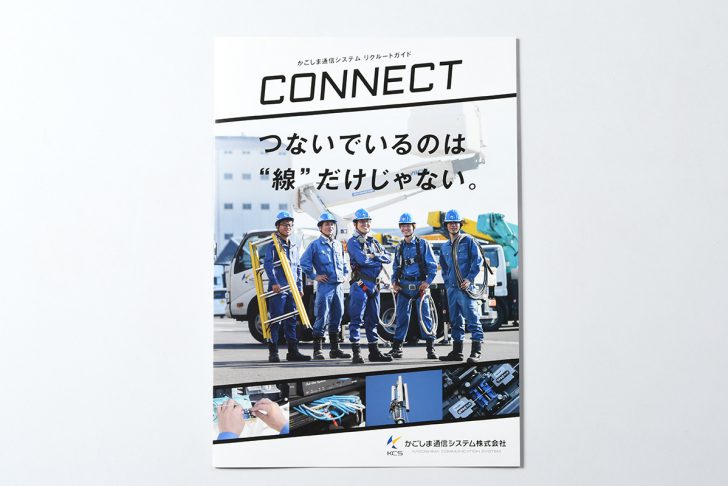
かごしま通信システム リクルートガイド
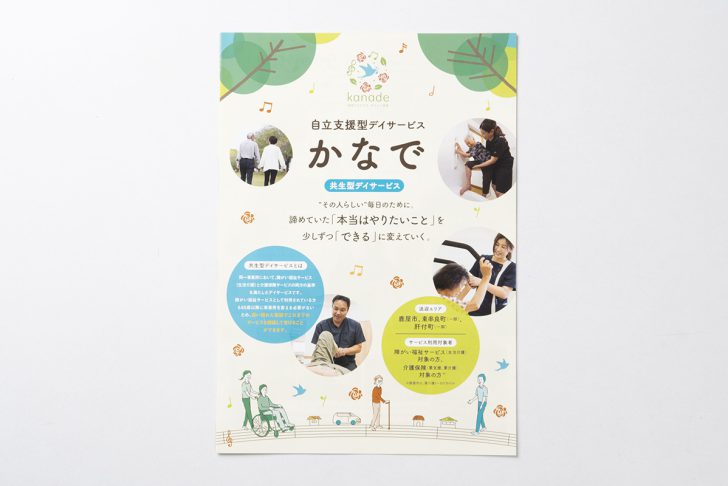
自立支援型デイサービス かなで リーフレット・チラシ
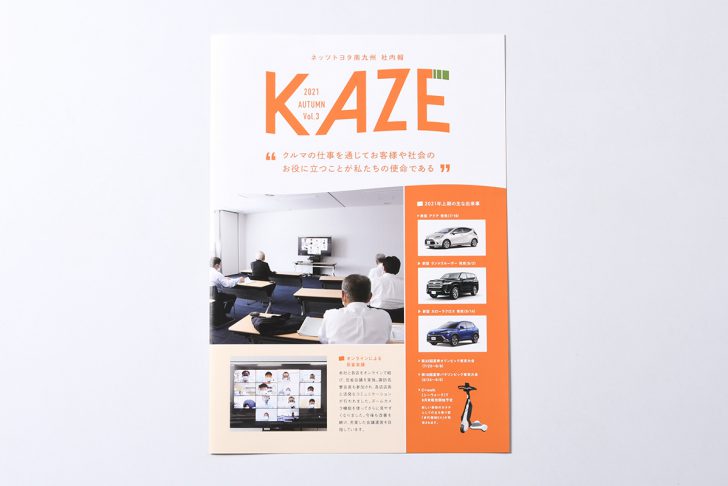
ネッツトヨタ南九州株式会社 社内報「KAZE」2021 AUTUMN
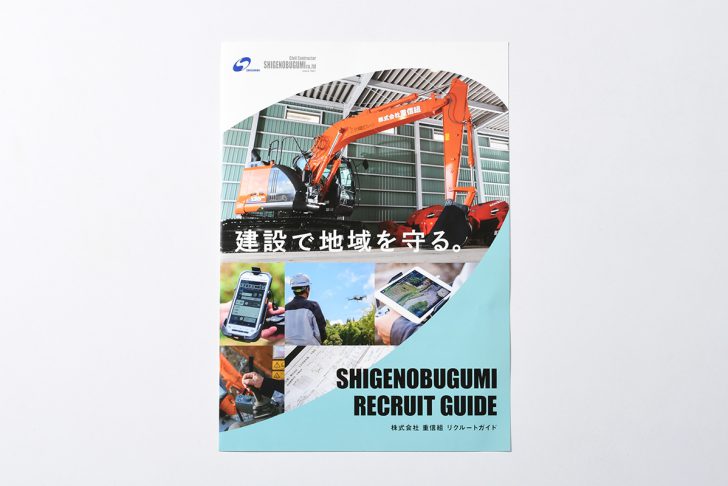
株式会社 重信組 リクルートガイド